 今日は特に用事がなかったので、先日ジャンクで手に入れたCASIO製5.0Mpixelデジタルカメラ「QV-R51」の周辺機器もろもろをあさりに行った。おおざっぱな人間のくせに、どうもこうしたデジタルガジェットはきれいに使いたいほうなので、液晶の保護フィルムをまず探してみる。まず最初に買ったのが、ELECOM DGP-003G 液晶保護フィルム(2.0型液晶用)
今日は特に用事がなかったので、先日ジャンクで手に入れたCASIO製5.0Mpixelデジタルカメラ「QV-R51」の周辺機器もろもろをあさりに行った。おおざっぱな人間のくせに、どうもこうしたデジタルガジェットはきれいに使いたいほうなので、液晶の保護フィルムをまず探してみる。まず最初に買ったのが、ELECOM DGP-003G 液晶保護フィルム(2.0型液晶用) 。QV-R51の仕様表には液晶が「2.0型」と書いてあったので買ってみたのだが、張ってみるとどうも大きさが小さすぎて合わない。液晶のまわりがアクリルでブラックアウトしてあるので、その大きさの分だけサイズが合わないようだ。結局、auのW31SA用の液晶保護フィルムがサイズ的にバッチリだったので、これを購入@350円。ケースについては、このサイズのカメラなら豊富なんだけど、使い勝手を考えて、これまたELECOM製のスナップ式ベルトループ付デジタルカメラケース
。QV-R51の仕様表には液晶が「2.0型」と書いてあったので買ってみたのだが、張ってみるとどうも大きさが小さすぎて合わない。液晶のまわりがアクリルでブラックアウトしてあるので、その大きさの分だけサイズが合わないようだ。結局、auのW31SA用の液晶保護フィルムがサイズ的にバッチリだったので、これを購入@350円。ケースについては、このサイズのカメラなら豊富なんだけど、使い勝手を考えて、これまたELECOM製のスナップ式ベルトループ付デジタルカメラケース を買った@770円。ちょっと余裕がある感じだけど、ストラップもついていて結構便利。が、どちらもamazonで買っておけばもっと安かったんだなあと反省。サイズの合わなかった液晶保護フィルムは、父親が使っているPENTAXのOptio S40に使うことにしました。
を買った@770円。ちょっと余裕がある感じだけど、ストラップもついていて結構便利。が、どちらもamazonで買っておけばもっと安かったんだなあと反省。サイズの合わなかった液晶保護フィルムは、父親が使っているPENTAXのOptio S40に使うことにしました。
 さて、本題。これまでサブで使っていたSonyのDSC-P1との機能差をチェックしてみました。いやまあ、明らかに世代が違うので、アマチュア球団と阪神が戦うようなものだってことはわかってますが、とりあえずチェックしておこうと思ったわけで(汗)。ただ、前のエントリにも少し書いたと思うんだけど、デジカメ業界は価格競争が起こってから、CCDなりCMOSのサイズは変えないでただひたすらスペック上の画素数を上げるという方向に向かってしまったので、実は画素数のほど画質はアップしていない。そういう意味では、DSC-P1はデジタルカメラ業界が価格競争に飲み込まれる以前の機種なので、CCDがどれだけ高性能だった(あえて過去形で)のか、少し期待しているところもあるのだけれど。何せ発表当時(2000年9月)の価格は99,800円というのだから、価格だけはいまの一眼なみだ(笑)。
さて、本題。これまでサブで使っていたSonyのDSC-P1との機能差をチェックしてみました。いやまあ、明らかに世代が違うので、アマチュア球団と阪神が戦うようなものだってことはわかってますが、とりあえずチェックしておこうと思ったわけで(汗)。ただ、前のエントリにも少し書いたと思うんだけど、デジカメ業界は価格競争が起こってから、CCDなりCMOSのサイズは変えないでただひたすらスペック上の画素数を上げるという方向に向かってしまったので、実は画素数のほど画質はアップしていない。そういう意味では、DSC-P1はデジタルカメラ業界が価格競争に飲み込まれる以前の機種なので、CCDがどれだけ高性能だった(あえて過去形で)のか、少し期待しているところもあるのだけれど。何せ発表当時(2000年9月)の価格は99,800円というのだから、価格だけはいまの一眼なみだ(笑)。
まず、実写チェックに入る前に、両機のスペックを簡単に併記しておきましょう。
●CASIO QV-R51
発売時期: 2004年1月
撮像素子:1/1.8型正方画素原色CCD(総画素数 : 525万画素)
レンズ: F2.8−4.9 f=8−24mm(35mmフィルム換算39〜117mm相当)
ズーム倍率: 光学3倍ズーム
ISO: 50~400で自動
●SONY Cyber-shot DSC-P1
発売時期: 2000年9月
撮像素子: 1/1.8型CCD(インターレーススキャン/原色フィルター)334万画素
レンズ: F2.8〜5.3 f=8〜24mm(39〜117mm)
ズーム倍率: 光学3倍ズーム
ISO: 不明(スペック表に記載なし)
焦点距離や光学ズーム倍率は両機に差はない模様。起動の早さやメモリの読み込みスピードなんかは明らかにQV-R51の勝ちだけど、4年の差があれば、それは致し方ないところ。CCDの大きさはほぼ同じで、同じサイズに160万ほど多くの画素を詰め込んでいるのが前者、ということになります。さてさて、両者の実力差やいかに?
簡単モード対決1:広角側
コンパクトカメラは設定はカメラ任せで気楽に撮ろう、という感じなので、完全オートで撮影したものを比較してみたいと思います。まずは広角側で撮った写真。撮影時は曇天。
●CASIO QV-R51(2.0MB)

QV-R51では、ISO感度が自動的に200に設定され、フラッシュは発光しなかった。シャッタースピードは1/60、絞りはF2.8でした。
●SONY DSC-P1(1.3MB)

それに対してDSC-P1では、ISO感度が100に設定され、フラッシュが発光した。シャッタースピードは1/60、絞りはF2.8で、このあたりの設定はQV-R51と同じになりました。
この二つの写真を比べてみると、QV-R51の方は、かなり明るめになっているのに対して、DSC-P1のほうは、少し重めの写り。が、実際の色味はどちらかというと後者の方が近いかな、という感じ。どうもQV-R51はかなり色をビビッドに表現するクセがあるみたい。色味はDSC-P1の方が近いけども、細部の描写に関しては、やはりQV-R51のほうに分があるかな。特に奥の方にある花の描写は、圧倒的にQV-R51のほうがきれい。
簡単モード対決2:望遠側
つづいて、望遠側の画像をチェックしてみます。こちらも撮影時は曇天。
●CASIO QV-R51(2.0MB)

かなり風が強かったせいか、なかなかピンあわせが難しかったんですが、こちらはシャッタースピード1/60、絞りF4.9、ISO200、フラッシュ発光。
●SONY DSC-P1(1.3MB)

広角とは対照的に、こちらはISOが282という中途半端な数字に設定され、フラッシュは発光せず。シャッタースピードは1/40、絞りF5.6での撮影になりました。
望遠側では、どちらかというとDSC-P1のほうはメリハリがなく、ちょっとホワイトバランスが崩れている印象を受けます。それに対してQV-R51は、ダイナミックレンジも広く、自然な発色になっています。望遠側では明らかにQV-R51のほうがいい絵が撮れていると思います。
まとめ
というわけで、簡単モードでの撮影をまとめてみると、やはり全体的にはQV-R51のほうが写りがいい。両機の年代差が4年あることを考えると、当たり前といえば当たり前。特に使い勝手に関しては、カメラのレスポンス、メモリーカードからの映像の読み込みには圧倒的にQV-R51の方が早いし、撮影した映像の再生に関しても、QV-R51にはヒストグラムを表示できたり、撮影情報を確認できるなどの利点がある。DSC-P1では、撮影条件を知るためには、一度Macに取り込む必要があり、ビューアーを通してExifをみるしかない。つまり、カメラ側でExifの情報を知ることができない仕様になっている。これはちょっと面食らってしまった。
こう書くと、まるでDSC-P1が全くだめ、という感じを受けてしまうかもしれませんが、僕はむしろDSC-P1は結構頑張っていると思っています。特に広角側の画質に関しては、DSC-P1とQV-R51の間に4年という差があるとはわからないほど、DSC-P1ががんばってるな、と感じます。やっぱりこのあたりは、当時のカメラのほうがしっかりとCCDが作られていた、ということなのかもしれないし、詐欺のようなスペックアップの影響なのかもしれないですな。レスポンスの良さとかは当時の技術水準があっただろうから、DSC-P1が劣るのは当たり前の話なわけで。4年という歳月の中で、光学ズームの画質がかなりこなれてきた結果なのかもしれない(2000年当時のデジタルカメラって、ほとんどがデジタルズームだけだったもんね)。あとは、「簡単に撮って楽しめる」だけのカメラから、「簡単にとって楽しめるし、ある程度まではマニュアル調整もできて楽しめる」カメラへのパラダイムシフトが起こった、っていうことなのかも。
また時間が空いたら、今度は接写の性能もチェックしてみたいと思っています。



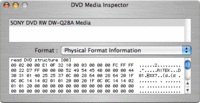










最近のコメント